第七十一章 頂点の影
法廷の空気は、これまで以上に緊迫していた。
内部メールという“決定的証拠”が提出されたことで、これまで防御一辺倒だった検察は一気に攻勢に転じた。次に狙うのは――経営陣。組織の頂点に立つ人間たちである。
- 証人申請の衝撃
ある日の開廷で、西村検事が毅然とした声で口を開いた。
「裁判長。検察は、新たに証人として、当時のJR西日本社長・城戸俊彦氏の出廷を申請いたします」
傍聴席がざわめいた。
城戸は事故当時、会社の顔として連日記者会見に臨んだ人物だが、これまで一貫して「現場からの報告を受けて動いていただけ」と責任の所在を巧みにかわしてきた。マスコミも度々突っ込んだ質問を投げたが、曖昧な回答しか返ってこなかった。
ついにその城戸が、法廷に呼ばれるのだ。
弁護人・宮坂が即座に異議を唱える。
「裁判長! 社長経験者を証人として呼ぶのは過剰です。現場の判断に任せていたことはすでに明らかであり、証言の必要性はありません」
しかし裁判長・村瀬は冷静に応じた。
「証人申請は採用します。事故当時の最高責任者が、何を知り、どのように判断していたかを確認することは極めて重要です」
木槌が鳴った瞬間、傍聴席からどよめきが走った。記者たちは一斉にメモを取り、遺族たちは小さく頷き合った。
- 社長の出廷
一週間後、ついにその日が訪れた。
法廷の扉が開き、グレーのスーツに身を包んだ城戸俊彦が入廷する。年齢は60代半ば、痩せて背筋は伸びているが、その表情には疲労と緊張の色が濃い。
証人席に腰を下ろすと、場内の視線が一斉に注がれた。
遺族の一人が思わず口にした。
「……あの人が……」
裁判長が証人尋問の開始を告げ、西村検事が立ち上がる。
- 検察の追及
「城戸証人。あなたは事故直後に社内で開かれた緊急会議に出席していましたね?」
「……はい、そうです」
「その会議で、運転士個人の過失を前面に出すよう指示した記録が残っています。事実ですか?」
城戸は表情を固くした。
「私は……報告を受けただけで、具体的な文言を指示したわけではありません」
西村はすかさず、例のメールを掲げた。
「この文書をご覧ください。“会社に不利な要素は削除せよ”という方針が、あなたが出席した会議直後に発信されています。証人、これは偶然ではありませんね?」
場内がざわつく。
城戸は眼鏡を外し、額に浮かんだ汗を拭った。
「……あの時は混乱していたのです。まずは社会への説明責任を果たすために、分かりやすい形で原因を提示する必要がありました」
「分かりやすい形、ですか。つまり“運転士だけの責任”に単純化することで、会社の責任を隠したのでは?」
城戸は唇を噛み、視線を落とした。
- 弁護側の反撃
ここで弁護人・宮坂が立ち上がった。
「異議あり! 検察は“隠蔽”と決めつけていますが、事故直後に混乱の中で情報を取捨選択するのは危機管理として当然です。証人は組織の長として、社会不安を最小限に抑える責務を果たしただけです!」
裁判長は一拍置いて言った。
「異議は却下します。証人、答弁を続けなさい」
城戸は椅子の背に寄りかかり、深く息を吐いた。
- 証人の沈黙と爆発
検事が再び問い詰める。
「証人。ATS未設置区間について、国交省からの指摘が事故前からあったことをご存知でしたか?」
「……知っていました」
「それにもかかわらず、設置を後回しにした理由は?」
城戸は口をつぐんだ。
法廷に沈黙が広がる。
遺族席から抑えきれない声が飛んだ。
「だから娘が死んだんだろう!」
「命を軽く見た結果じゃないか!」
裁判長が木槌を叩き、静粛を促す。だが怒号は完全には収まらなかった。
西村検事は声を張り上げた。
「証人! あなたはコスト削減を優先し、安全対策を後回しにした。その事実を認めるのですか!」
城戸の手が震えた。顔は蒼白になり、口元は小刻みに動いたが、声は出なかった。
- 廊下の記者会見
休廷になると、廊下は記者団で埋め尽くされた。
「ついに社長が追及されましたね」「核心に迫ったぞ」――そんな声が飛び交う。
遺族の代表の一人がマイクの前に立ち、涙ながらに語った。
「やっとここまで来ました。でも、まだ“真実の名前”は語られていません。誰が決断したのか、誰が命より会社を選んだのか、それを必ず明らかにしてほしい」
その言葉がテレビカメラを通じて全国に流れ、人々の心を揺さぶった。
- 弁護団の焦燥
夜、弁護団の控室では、宮坂が頭を抱えていた。
「まずい……このままでは役員会全体に火の粉が及ぶ」
若手弁護士が恐る恐る口を開いた。
「証人が沈黙したのは逆効果でした。世間は“隠している”と見ています」
宮坂は苦い顔でうなずいた。
「次の一手を考えねばならん……」
- 検察の決意
一方、検察庁では西村が資料を前に固い表情をしていた。
「次は役員会の議事録だ。そこに真実が残っているはずだ」
彼の脳裏に浮かぶのは、崩れた車両の残骸、そして遺族の涙。
――必ず核心にたどり着く。
- 闇の頂点
その夜、城戸は自宅の書斎でひとり座っていた。
窓の外には梅雨の雨が叩きつけ、静かな部屋に重い響きを残していた。
机の上には分厚い議事録のコピー。そこには、自分の署名がはっきりと残っている。
「……あのとき、私は……」
声は小さく震えていた。
その姿は、組織の頂点に立ちながらも、自ら築いた影に囚われた男の姿だった。
裁判は、ついに組織の核心へと踏み込んだ。
――次に暴かれるのは、誰なのか。
第七十二章 議事録の告発
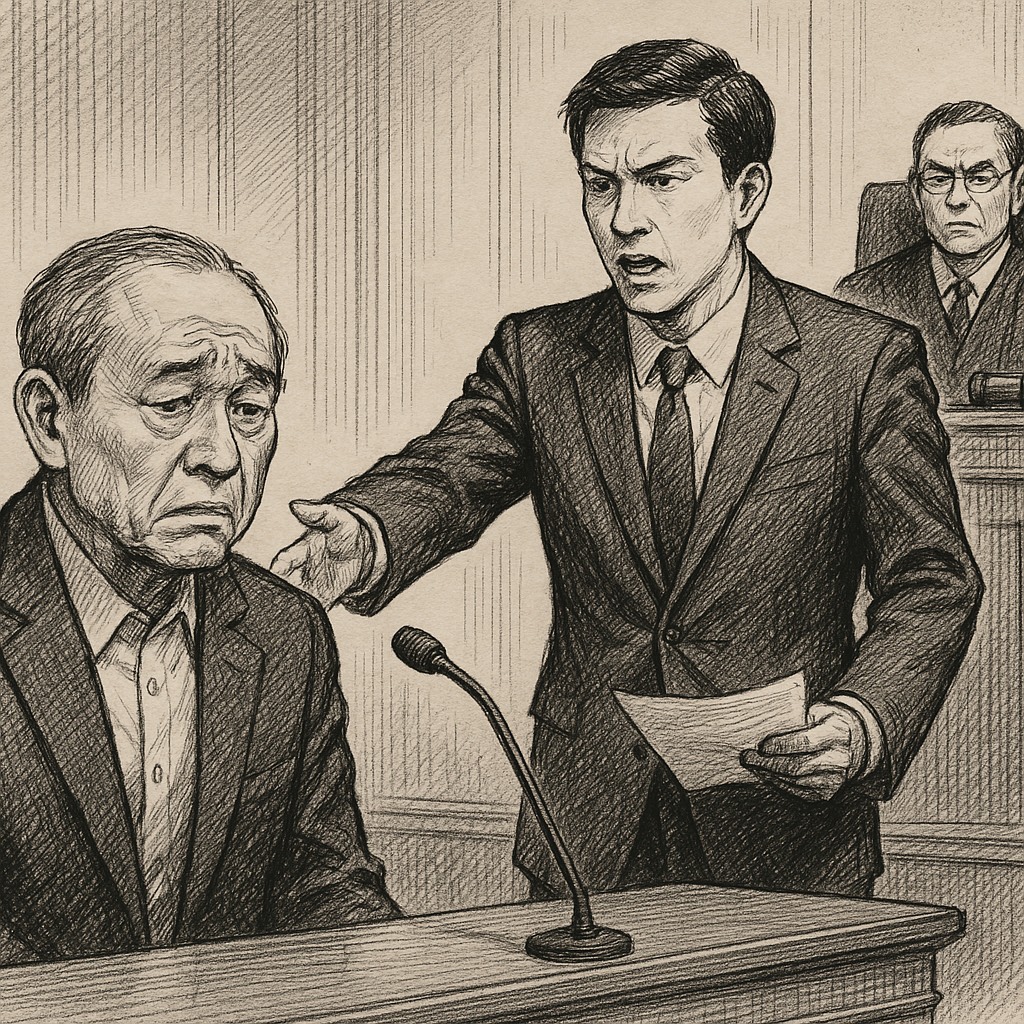
- 開廷前のざわめき
六月の湿った空気が神戸地裁の廊下を覆っていた。
記者たちは早くから集まり、マイクとカメラを構えている。今日の審理で、検察が“新たな内部資料”を提示するという情報が広まっていたからだ。
傍聴席の遺族も、いつも以上に多く集まっていた。年配の母親が亡き息子の遺影をバッグに忍ばせ、静かに祈るように座っている。その隣で、若い女性がハンカチを握りしめ、緊張で唇を噛んでいた。
扉が開き、裁判長・村瀬が入廷すると、場内は一斉に静まり返った。
- 検察の提示
検事席に立った西村は、分厚いバインダーを抱えていた。
「裁判長、検察は新たな証拠を提出いたします。これは事故発生直後に開かれた役員会議の議事録です。複数の元社員から提供を受け、真正性は専門家によって確認されています」
傍聴席にどよめきが走った。
弁護人・宮坂が即座に立ち上がる。
「異議あり! 内部告発者の匿名性を盾にした証拠など、信憑性に欠けます」
西村は冷静に返した。
「しかし、ここに記された内容と、すでに提出済みのメールの文面が完全に一致している。二つが独立した資料から導かれている以上、偶然ではありません」
裁判長は議事録の束を受け取り、重々しくページをめくった。目を走らせるうちに、眉間に皺が寄る。
「……これは……」
- 議事録の中身
西村が朗読を始めた。
「事故発生翌日の会議において、当時の経営企画室長がこう述べています。『このままでは会社の存続が危うい。報告書は運転士の速度超過を主因とし、管理体制の不備は記載しないこと』」
会場に衝撃が走った。遺族の一人が小さく「やっぱり……」とつぶやき、周囲の目から涙があふれ出した。
さらにページを繰り、西村が続ける。
「『ATS未設置の件は、財務上の事情により延期せざるを得なかった。だが、この点は一切外部に出すな』」
傍聴席から怒号が飛んだ。
「金のために命を削ったのか!」
「娘を返せ!」
裁判長が木槌を叩き、制止したが、その声は容易に収まらなかった。
- 弁護側の反論
宮坂弁護士が立ち上がり、声を張った。
「この議事録はあくまで“草案”に過ぎません。実際の会議で正式に決定された事項ではない。しかも、告発者は匿名。個人的な恨みから虚偽を混ぜた可能性もある」
西村は即座に反論した。
「ならば、なぜ複数の告発者が同じ文言を証言しているのか? さらに議事録の末尾には、当時の社長・城戸証人の署名と押印が残っています」
城戸の名が出た瞬間、場内は再びざわついた。
- 城戸の動揺
証人席の片隅に呼び戻されていた城戸俊彦は、顔色を失っていた。
裁判長が問う。
「城戸証人。この署名は、あなたのもので間違いありませんか?」
城戸は眼鏡を外し、両手で額を覆った。
「……確かに、私の署名です。しかし……私は細部を承知していたわけではない……」
検事が畳みかける。
「署名とは“承認”の意味を持つのです。あなたは議事録を確認し、会社の責任を外部に隠す方針に同意した。その事実を否定できますか!」
城戸の肩が震え、唇が小刻みに動いた。だが、言葉は出なかった。
- 告発者の証言
ここで検察は、匿名を条件に出廷した元役員補佐の証言を提示した。
スクリーンに映し出されたのは、声だけを変えた録音だった。
『あの会議では、最初に安全部がATS未設置の責任について説明しようとしました。ですが経営企画室長が遮り、“それを入れれば株価が暴落する。運転士一人の過失に絞れ”と強く主張したのです。社長も最終的に黙認しました』
この証言に、遺族席は嗚咽で満たされた。
「やっぱり……会社ぐるみで……」
- 裁判長の言葉
裁判長・村瀬は深くため息をつき、木槌を叩いた。
「本件は、もはや単なる現場の過失を超えている。組織の頂点において、安全よりも経営を優先したのではないか――その疑いが強まった」
その言葉は、法廷の全員に重く響いた。
- 廊下の熱気
休廷となり、廊下に出た記者たちは一斉に電話をかけ、原稿を書き始めた。
「隠蔽議事録、社長署名!」「企業責任、決定的段階に!」
フラッシュが絶え間なく光り、遺族は記者のマイクに向かって声を絞り出した。
「うちの子の命を数字と同じに扱ったのかと思うと、胸が張り裂けそうです……」
- 弁護団の窮地
弁護団の会議室では、宮坂が苦渋の表情を浮かべていた。
「議事録に署名がある以上、抗弁は難しい。あとは“手続き的瑕疵”を突くしかない」
若手弁護士が震える声で言った。
「ですが、世論は完全に会社を敵に回しています。勝ち筋は……」
宮坂は黙って天井を仰いだ。
――法廷の論理と世論、その両方に押し潰されそうだった。
- 城戸の独白
その夜、城戸は自宅の書斎にひとり籠もっていた。
机の上には議事録のコピー。署名の部分をじっと見つめながら、彼は小さく呟いた。
「……あの時、私は会社を守ろうとした。だが、それは百七人の命を踏みにじることだったのか……」
窓の外で雨が降り続いていた。
城戸の目から、初めてひとすじの涙がこぼれ落ちた。
- 次なる焦点
検察はすでに次の証人を準備していた。それは、経営企画室長本人。議事録に名を刻んだ張本人であり、隠蔽方針を主導したとされる男である。
西村はデスクで資料を整理しながら、静かに拳を握った。
「次は――逃さない」
裁判は、組織の闇の核心へ。
安全よりも利益を優先した決断の真相が、いよいよ白日の下にさらされようとしていた。
(第七十三章につづく)
※この小説はフィクションであり、実在の人物や団体とは一部の史実を除き関係ありません。西村京太郎風のリアリズムを重視し、架空の登場人物を通じて事件の構造に迫っていく構成になっています。









コメント