第五十五章 静寂の中の影
五月の空は澄み渡り、法廷の窓から射し込む光が木製の机を柔らかく照らしていた。だが、その明るさは決して人々の心を和らげるものではなく、むしろ現実の冷徹さを強調する役割を果たしていた。
福知山線脱線事故をめぐる長大な裁判は、ついに終盤に差しかかっていた。これまでの審理で積み重ねられた証拠と証言は膨大で、傍聴席に並ぶ遺族たちの顔には、疲労と憔悴が深く刻まれている。それでも彼らは法廷に通い続けていた。亡くなった家族のために、真実を確かめるまでは背を向けられなかった。
検察官の朗々とした言葉が途切れ、法廷に一瞬の沈黙が訪れる。椅子がきしむ音さえ、不釣り合いに大きく響いた。
やがて証言台に呼ばれたのは、事故当時、運行管理室に勤務していた中年の男性だった。痩せた体躯にくたびれたスーツをまとい、緊張からか額に細かい汗が滲んでいる。
「あなたが事故当日、運行管理システムに入力した記録に誤りがある、との指摘があります。説明していただけますか」
裁判長の低い声が響いた。証人は一瞬、言葉を失ったように口をつぐんだ。傍聴席から注がれる無数の視線。その中には、命を奪われた家族のために真実を求め続ける人々の無言の問いかけがあった。
証人は乾いた唇を舌で湿らせると、ようやく声を絞り出した。
「……私が入力した時点で、すでに現場からの情報は矛盾していました。報告書のフォーマットにも無理がありました。私は上司に修正の必要を訴えましたが……そのまま処理するように命じられたのです」
その言葉が発せられた瞬間、傍聴席から抑えきれないざわめきが漏れた。遺族の誰かが小さく声を上げる。
「それでは、最初から真実は歪められていたのか……」
裁判官の木槌が三度打ち鳴らされ、場の静寂が無理やり取り戻された。
十津川省三は傍聴席の一角に座り、その光景を静かに見つめていた。だが、彼の注意は証言内容よりも、別の一点に向けられていた。
傍聴席の端に、一人の男が紛れていた。深く帽子をかぶり、無精ひげを伸ばした中年男。周囲の傍聴人と違い、彼の眼差しは異様に鋭く、証人の言葉を一字一句逃すまいと凝視している。
――あの顔、どこかで……。
十津川の記憶の奥底に、過去の捜査記録が蘇る。鉄道関連の不正事件で名前が浮上し、しかし消息を絶った男。
尋問が終わり、裁判は短い休廷に入った。人々が一斉に立ち上がり、廊下へと流れ出す。ざわめきの中、十津川は素早く席を立ち、その男を追った。
だが、廊下に出たときには、すでに姿は見えなくなっていた。人の波に紛れ、影のように消えてしまったのだ。代わりに床に、一枚の紙切れが落ちていた。
拾い上げると、それは鉄道の運行ダイヤの断片だった。赤いペンで大きく「影の時刻」と記されている。
「影の時刻……?」
呟いた十津川の胸に、不安と疑念が膨らんでいく。
その夜、ホテルの部屋に戻った十津川は、机いっぱいに広げた資料に目を落とした。事故当時の運行記録、運転士の労務管理票、現場で発見された時計の写真――。
そこに一つの矛盾が浮かび上がっていた。
事故直後に提出された運行記録の時刻と、運転士の腕時計の針が示す時刻。その間には数分の差がある。鉄道の世界で「数分」は、軽視できる誤差ではない。運行管理、信号システム、すべての調和を揺るがす致命的な齟齬だった。
もしその数分の差が「影の時刻」と呼ばれるものだとすれば――。
誰かが意図的に時刻を操作し、事故の責任を曖昧にしようとしているのではないか。
電話が鳴った。受話器を取ると、亀井刑事の声が聞こえた。
「十津川さん、気になる情報が入ったよ。今日の傍聴に来ていた不審な男、あれは元JR関連会社の職員だった。数年前、内部告発を試みたが、直後に姿を消したらしい」
「やはり……。その男が残していった紙には『影の時刻』と書かれていた」
「影の時刻?」
「そうだ。まだ意味は掴めないが、裁判の表舞台とは別に、裏で仕組まれた時間の操作があるのかもしれない」
二人は翌日の行動を確認し合い、通話を終えた。
十津川は机に肘をつき、窓の外を見やった。夜の街を列車の光が横切り、車輪の響きがかすかに届く。その音が、彼に現実の冷たさを思い知らせた。
彼は決意を固めた。裁判がどれほど進もうとも、影の真実を突き止めなければならない。遺族の涙も、社会の憤りも、真実を解き明かすことでしか救えないのだ。
夜更け、机上の資料の中で、赤い文字で記された「影の時刻」がなおも十津川の視界にちらついていた。まるで、まだ語られていない秘密を告げる暗号のように。
そして翌朝。
裁判所の玄関に立つ十津川は、冷たい風を胸に吸い込んだ。
これから彼が挑むのは、表向きの審理を超えた、もうひとつの物語だった。
人々の影に潜むもの、それを暴かなければならない。
静寂の中で揺れる影の奥に、真実は確かに潜んでいる。十津川はそう確信して、法廷の扉を押し開けた。
第五十六章 影の時刻の正体
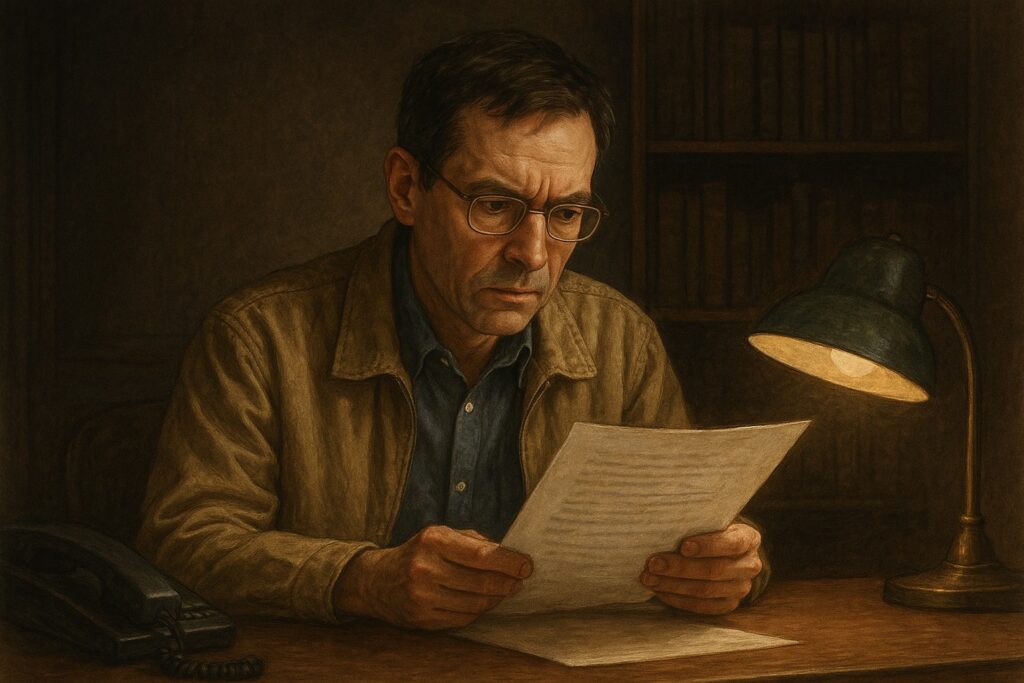
午前十時。裁判所の重い扉が開かれ、今日も傍聴人たちが列をなして法廷へと吸い込まれていった。
人々の顔には、昨日までの証言が残した衝撃が色濃く刻まれていた。運行管理室での記録改ざんを示唆する発言、そして姿を消した不審な傍聴人。裁判が単なる事故原因の究明ではなく、より深い闇へと踏み込もうとしていることを、誰もが感じていた。
十津川省三は法廷に入る前、廊下の片隅で立ち止まった。手にした封筒の中には、昨夜、亀井が入手した資料のコピーが収められている。
それは事故当日の運行ダイヤと、管理システムに残された電子ログの照合結果だった。驚くべきことに、両者の間には明確な齟齬が存在していた。電子ログの時刻が、実際のダイヤより常に二分進んでいたのである。
「つまり……『影の時刻』とは、この二分のことか」
十津川は呟いた。鉄道の世界で二分は致命的なずれだ。ブレーキ操作、信号現示、指令室の判断、そのすべてが狂わされる可能性を孕んでいる。
やがて開廷の合図が鳴り響いた。
裁判長が席に着き、静寂が広がる。その空気を切り裂くように、検察官が立ち上がった。
「次に提出するのは、事故当日の運行管理システムの電子記録です。ご覧の通り、時刻は実際の列車運行と一致しておりません」
スクリーンに投影された資料に、傍聴席からどよめきが起こる。数字の列が示すのは、確かに二分のずれ。しかも、そのずれは事故発生の直前から顕著に現れていた。
弁護側が即座に反論する。
「機械の誤作動、あるいは入力者の単純なミスではないでしょうか。電子機器に誤差はつきものです」
しかし、検察官の声は揺らがなかった。
「もし誤差だとするなら、なぜ常に同じ方向に二分だけ進んでいるのでしょう。偶然にしてはあまりにも不自然です」
裁判官の視線が鋭く弁護側に向けられた。その瞬間、傍聴席の一角で、誰かが小さくうめき声を上げた。
十津川はすぐに振り返った。昨日見失ったあの男――無精ひげを生やした元職員が、傍聴席の隅に座っていた。
彼の手には、小さなノートが握られている。そのページにはびっしりと手書きの数字が並び、何度も赤線で「二分」と書き込まれていた。
休廷の合図が告げられるや否や、十津川は素早く男に近づいた。
「あなたが『影の時刻』を知っているのではないですか」
低く問いかけると、男の肩が震えた。
「……俺は、口を閉ざすように言われていた。だが、もう限界だ。あの日、システムの時計は意図的に操作されていたんだ」
言葉は途切れ途切れだったが、十分だった。十津川は彼を控室へ連れ出した。
男は名を中里と言った。かつてJR関連会社のシステム部門で働き、運行管理ソフトの保守を担当していた。
「システムの時計は通常、GPSと同期していて狂うことはない。だが、上層部の指示で一時的に独立モードに切り替えられた。その結果、二分進められた状態で固定されたんだ」
「なぜそんなことを?」
「遅延を小さく見せかけるためだ。列車が定刻に近い数字で走っていたと記録されれば、運転士の責任に押しつけられる。システムのずれは、会社にとって都合のいい“影”になった」
十津川の胸に、怒りが込み上げてきた。
つまり「影の時刻」とは、会社ぐるみで仕組まれた隠蔽工作の象徴だったのだ。二分進められた時計は、運転士の判断を狂わせ、事故の責任を一個人に押し付けるための罠に過ぎなかった。
「中里さん、その事実を法廷で証言していただけますか」
しばらくの沈黙の後、男は深くうなずいた。
「……もう逃げない。俺も、あの日から心を蝕まれてきた。真実を話すことでしか、救われない」
午後の法廷。証人席に立った中里の証言は、まさに爆弾だった。
彼は淡々と、システムの時計が意図的に操作された経緯を語り、内部の会議でのやりとりを明かした。
「影の時刻――それは、組織が自らの責任を覆い隠すために生み出した偽りの時間です」
その言葉が響いた瞬間、傍聴席は揺れた。遺族の目に涙が浮かび、拳を握りしめる者もいた。
裁判長は重々しく頷き、記録係に向かって指示を下した。
「ただいまの証言を、正式に記録する」
十津川はその光景を見届けながら、胸の奥に冷たい感触を覚えていた。
真実は暴かれた。だが、これはまだ始まりに過ぎない。影を作り出したのは誰か。どこまでが個人の判断で、どこからが組織の意思なのか。核心に迫ったようで、さらに深い闇が口を開けている。
休廷後、法廷を出た十津川の耳に、外の喧噪が押し寄せた。
記者たちが走り回り、マイクを突きつけ、誰もが「影の時刻」という言葉を口にしていた。社会は今、この隠蔽の構図に気づき始めたのだ。
だが十津川は、人波の向こうに立つ一人の男の姿を見逃さなかった。
黒いスーツを着た初老の男が、冷ややかな笑みを浮かべてこちらを見つめていた。
その目には、すでに次の一手を準備している者の確信が宿っていた。
十津川はその視線を受け止め、静かに歩みを止めた。
――核心を暴いたはずが、さらに大きな闇を呼び覚ましたのかもしれない。
夜風が吹き抜ける裁判所の階段の上で、十津川は思った。
影の時刻を作り出した者たちの正体を突き止めるまで、この戦いは終わらないのだ、と。
(第五十七章につづく)
※この小説はフィクションであり、実在の人物や団体とは一部の史実を除き関係ありません。西村京太郎風のリアリズムを重視し、架空の登場人物を通じて事件の構造に迫っていく構成になっています。









コメント